導入事例
電話中心の運用から脱却!QナビORDERで可視化・標準化・時短を実現

飲食店舗運営
株式会社
株式会社
カインズフードサービス
柳沢 武さま
店舗開発グループ
店舗開発·設計·設備担当
店舗開発·設計·設備担当
その他の導入事例
OTHER CASE
1/3
1/3






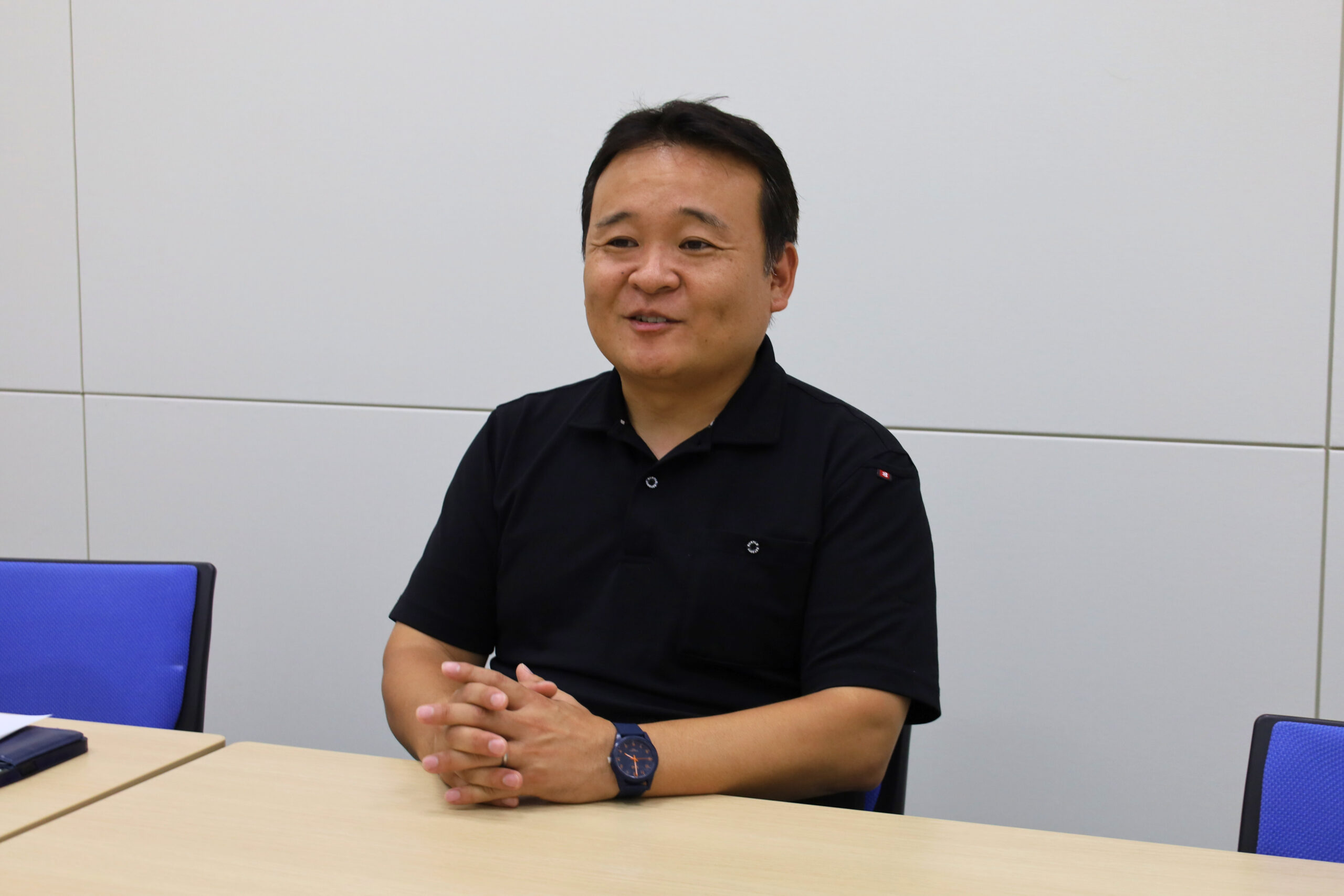










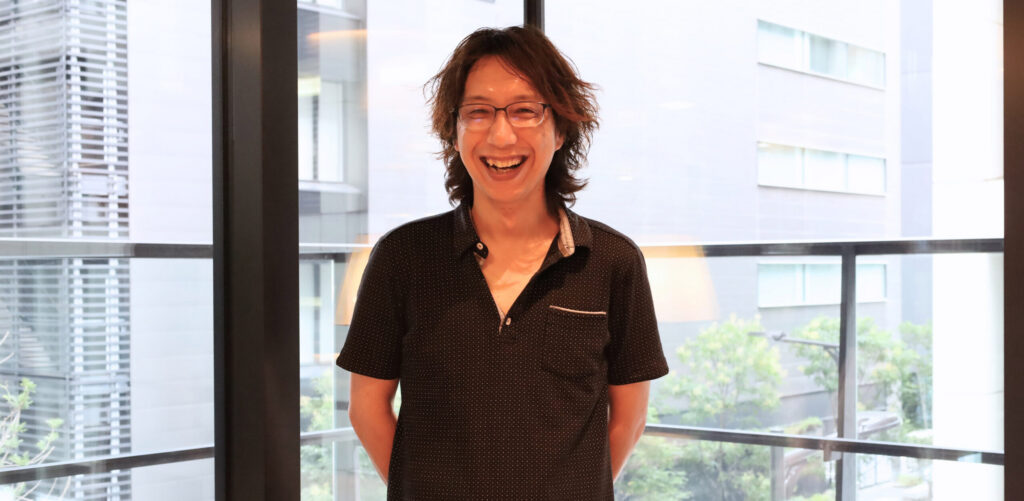



 03-3527-1020
03-3527-1020