導入事例
「店舗はお客様のために」を支える“右腕”。AIで進化するQナビがメンテナンスDXを将来的に牽引していく

株式会社壱番屋
ストアCS課
- 企業名
- 株式会社壱番屋
- 事業内容
- カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など
- 導入範囲
- 1,200店舗以上(本部導入)
Before 導入前
- 店舗からの依頼は電話・メールで受付。本部がコールセンターのシステムへ入力し、発注システムで協力会社さまへ依頼
- 業者からの回答を本部で再整理して店舗へメール連絡。橋渡しの事務負荷が大きい
- 機器や金額感の“暗黙知”が担当者に属人化し、人財の異動・育成が難しい。
After 導入後
- 本部の発注業務はQナビORDER(以下、Qナビ)に切替。見積・日程確定・報告など後工程はQナビ運用チームが並走。
- 本部とQナビ運用チーム間のやりとりはチャット中心で即時性が向上。
- 発注起票や見積書のやり取りが簡潔になり、本部は判断と品質管理に注力しやすくなった。
全国に「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開する株式会社壱番屋さまでは、Qナビを本部先行で導入。電話・メール起点は維持しつつ発注起票をQナビへ切り替え、見積・日程確定・報告の後工程は運用チームが並走する体制に移行しました。
本記事では、ストアクリエイション部 ストアCS課の吉田 悦典さま・鎌田 正輝さまに、導入前の課題、本部への先行導入で見えた効果と運用のコツ、今後のDX展望について伺いました。
CHAPTER 01
二重入力と時間制約を抱えた“本部ハブ”型運用
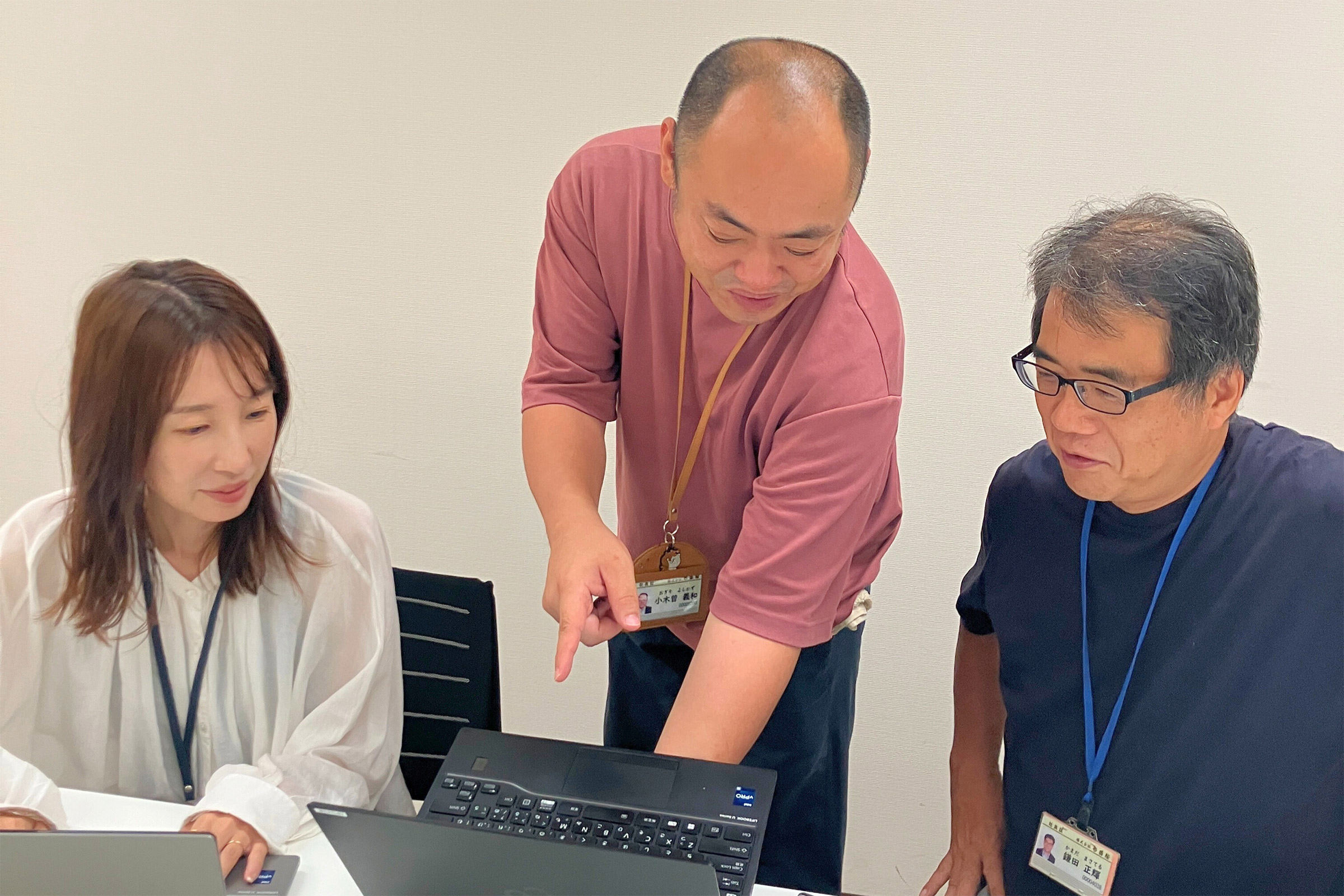
導入前の運用は、受付内容をコールセンターのシステムに入力し、そのあと手配先を選んで承認・送信する二段階の手続きです
「まず受付したら本部で入力して、その後に手配先を選んで承認して発注書を送る流れです。単純作業のようで1件1件時間を要していました」と鎌田さまは話します。
対応時間が日中に限られるため、繁忙期はどうしても滞留しがちで、「処理の途中に新しいメール受信や電話が入って、後手に回ることもあります」と続けます。
また、業者さまからの返答を受けて本部が内容を再整理し、店舗へメールで伝える“橋渡し”も時間を要していました。
「取引業者さまから戻ってきた内容を私たちが確認して、店舗にメールするので入力作業が多いのです」。
機器や金額感といった暗黙知が担当者に偏りやすく、知識の引き継ぎが難しいため、異動や育成にも影響が出ていたといいます。
CHAPTER 02
FC展開企業ならではの基本姿勢「店舗はお客様のために。本部は店舗のために。」

フランチャイズ比率の高い同社では、“お客様 最優先”の姿勢が直営店・加盟店を問わず徹底されています。
吉田さまは「ご来店いただけるお客様中心の考えであり、直営店と加盟店を区別することは絶対にない」と話し、
「店舗はお客様のために、本部は店舗のために」を軸に、空調故障のようなクリティカルな事象は区別なく至急案件として対応しているといいます。
さらに「加盟店、直営店に関係なく寄り添っていくところだと思っています」と続け、店舗支援のスタンスを明確にしています。
また、金額も加盟店オーナーにご納得いただけるよう案件ごとに価格確認を行っています。
吉田さまは「結局費用を負担するのはFCオーナーさまなので、承認や金額面の確認は、より慎重にご判断いただく場面が多い」と話します。
そのぶん本部には丁寧な説明と手続きが求められますが、現場対応のスピードや品質は“直営・加盟の区別なくお客様中心の考えで”保つ——これが同社の基本姿勢です。
CHAPTER 03
“アプリで依頼”の将来像と、トラブルNAVIへの期待
複数のソリューションを比較する中で、Qナビを選んだ最大の理由は「現場からアプリで依頼が完結する将来像」にありました。 加えて、依頼前に“いま現場でできる確認や応急対応”をガイドする「トラブルNAVI」のコンセプトにも強く惹かれています。
鎌田さまは「アプリで依頼できるっていうのが大きかったです。Webはあっても“アプリ”は見当たりませんでした」と話し、
「AIを使ったトラブルNAVIに期待しました。システム的に新しいことをやっていて、これからどんどん進化していくと感じました」
と先進性への期待を語ります。
さらにID設計についても、「オーナーIDを軸に複数店舗を束ねられるところが良かったです。1IDごとの課金だとコストが高くなるケースが多いので」と評価しています。
CHAPTER 04
本部への先行導入での運用「右腕ができた」という安心感
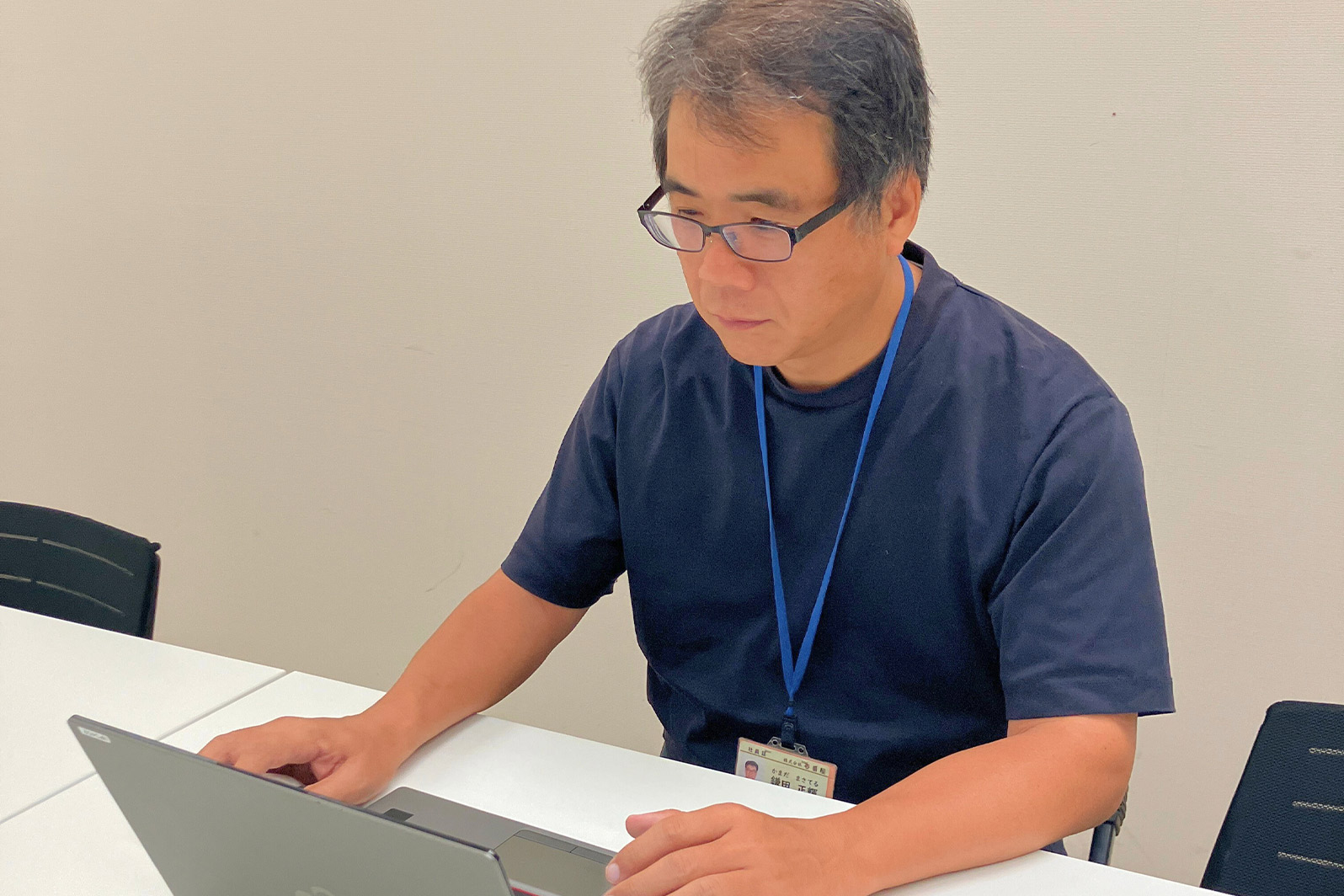
現在は国内全店舗をサポートする本部に先行導入し、発注起票をQナビに切り替え、見積・日程確定・報告などの後工程をQナビの運用チームが並走しています。 「自分たちとは別に動いてくれる人がいる安心感は大きいです」との声もあります。
夏場の空調など致命的影響を及ぼす案件が集中する時期に、Qナビの運用チームの協力で、現地調査や修理の訪問日時をできるだけ早く確定できる体制が着実に整ってきたと感じています。 「任せるところと自分たちの役割が明確になり、壱番屋の“右腕”的な存在になってきています」と吉田さまは話します。
コミュニケーション面では、本部とQナビ運用チーム間のチャットが即時性を発揮しています。 「電話で逐一確認していた場面も、チャットなら気軽に質問を入力できすぐ返ってきます」と実感が寄せられています。 あわせて、部内からは「発注起票や見積書のやり取りがぐっと楽になりました」との声も上がっているそうです。
CHAPTER 05
AIで「店内で解決」を広げる——トラブルNAVIと標準化で進めるメンテナンスDX
同社のメンテナンスDXにおける展望は、訪問前に店内で解決できるケースを増やせる状態を理想としています。 鎌田さまは「生成AIを活用した故障診断に期待しています」と話し、トラブルNAVIの進化により発注前の応急対応の幅が広がることを期待しています。
あわせて、型番や相場感、手配先といった暗黙知を仕組みに載せ、誰でも同じ水準で動ける状態を目指しています。「知識が専任化しがちなので、標準化していきたいです」
と吉田さまは語ります。
本部先行で可視化と承認フローを磨きつつ段階的にFCへ広げ、「店舗はお客様のために、本部は店舗のために」という原則をDXでより強く支えていきます。
その他の導入事例








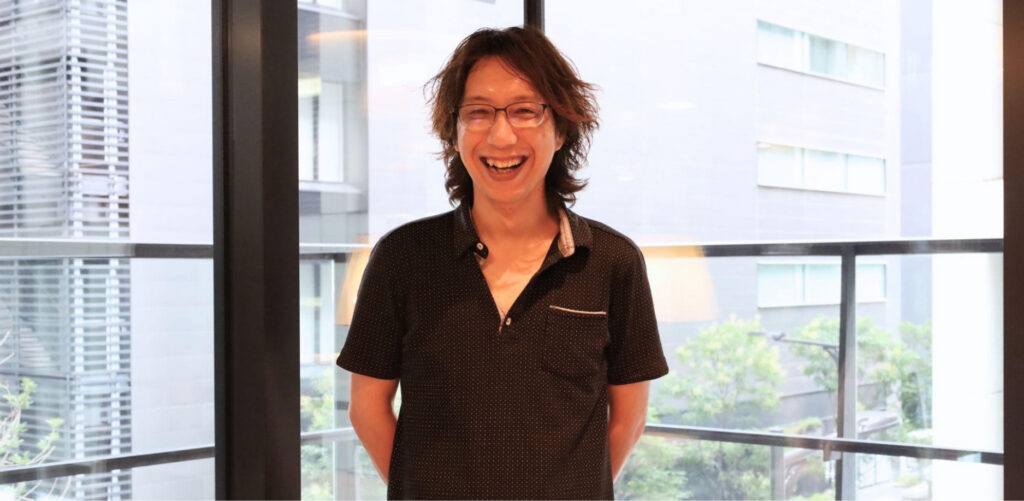



 03-3527-1020
03-3527-1020